【大阪・関西万博】コラム 多様でありながら、ひとつ「大屋根リング」に込めた思い

散策する来場者でにぎわう大屋根リング上のスカイウォーク。草花も植えられている
大阪・関西万博のシンボルとなっている「大屋根リング」は、建築家・藤本壮介さんが設計した。1周約2キロ、内径約615メートル、高さ約12メートル(外側約20メートル)。万博の会場デザインプロデューサーでもある藤本さんは、この世界最大の木造建築物にどんな思いを込め、未来につなげようと
ているのだろうか―。
ギネス世界記録に認定された「世界最大の木造建築物」
「分断が激しいこの時代に、世界の80%ぐらいの国・地域がこの場所に集まり、半年間一緒に過ごす。交流が生まれ、共に未来を考える。世界が一つのことを共有することは尊く、とてつもなく価値がある」。開幕直前に開催されたメディアデー(報道陣向け内覧会)。藤本さんは、大屋根リングの下でそう語った。
人類がコロナ禍を経て、「つながりを取り戻す万博」。大屋根リングは会場デザインの理念「多様でありながら、ひとつ」を体現するシンボルとして造ったという。地球にはさまざまな生態系があり、いのちの連鎖がある。多様性とは、文化や国を超えてつながることでもある。
建築家として、機能性や人の流れを考えた。「万博会場には東と西の2か所にゲートがある。中央に人が集中することを避けるため、ぐるっと回るのがスムーズだろう。そうすると円形が一番よいのでは」
2020年夏、藤本さんは他のプロデューサーと共にまだ更地だった夢洲(ゆめしま)を訪れた。「快晴で空が広く、雲が美しかった。それを見た時、『どんな会場設計をしても、この空にはかなわない。円形に切り取った一つの空を来場した皆さんが見上げることができる場所にしよう』と決めた」
1970年大阪万博で、「太陽の塔」が建物の大屋根を突き抜けるように切り取った「まあるい空」。そのイメージを受け継ぎ、55年後の万博では「空」そのものを主役に据えようと考えた。「空は地球を包んでいるから、実は地球上のどこから見上げても一つ。万博会場に来られない人でも、見上げている空は全部つながっているんですよね」というわけだ。
夢洲は護岸に囲まれた人工島であり、地上からは海が見えない。リングに上がれる構造にすることで、瀬戸内海の夕日や六甲山の山並み、大阪のビル群や関西国際空港などを望む。同時に、リングの内側に目を向ければ各国のパビリオンが見下ろせる。リングの上をぐるりと歩けば、町並みを巡るように景色も変わる。昼や夕暮れ、夜と時間帯によって、驚くほど違った表情を見せる。

大屋根リングの夕景。「リングに夕日が落ちていくのをみんなで見てほしい」と藤本さん
開幕を前に、大屋根リングは「世界最大の木造建築物」としてギネス世界記録に認定された。藤本さんが木造にこだわった理由の一つは、SDGsを達成するため環境に優しい建築材として注目が高まっているからだ。「日本には千年以上続く木造建築の技術があり、森林資源も豊か。それなのに現状は世界に遅れをとっており、もったいない」。日本が誇る伝統や技術を知ってもらうきっかけになればと考える。今回の万博でもチェコやドイツ、ウズベキスタンなどが木を使ってパビリオンを建てた。会場の中心には、自然との調和を目指し、「静けさの森」を配置した。
大阪・関西万博は、「海の万博」でもある。開幕後、私は夢洲会場を海上から見る機会があったが、リングの上から手を振る人々の姿が目に入り、船からも大きく手を振り返した。こんな楽しみ方があるのかと、四方を海に囲まれた万博会場の魅力を実感した

大屋根リングの下で弁当を広げる子どもたち。「リングを構成するユニット一つ一つは住宅サイズでできているので、居場所になりやすい」と藤本さん
リングの一部保存に向け、課題も
日本国際博覧会協会は6月下旬、閉幕後も大屋根リングの一部を人が上がれる状態で保存する方針を決めた。当初の計画では大屋根リングは閉幕後に撤去する予定だった。保存して長く使うためには、改修が必要。維持管理にも費用がかかり、具体的な方策も検討しなければならない。
藤本さんは6月中旬、万博会場のEXPOホールで開かれた建築カンファレンスで、大屋根リングの保存を巡る議論への思いを語った。
「建築は記憶の器と言われる。リングも皆さんの記憶に数十年残ってほしいと思って造った。初めは解体されるものだと思っていたが、(完成後は)実物を前に、なくなってもいいのかというとちょっと寂しいなと。これは記憶や想像力を超えている。建築にはそういった力があると思うようになった」
比べられるのは70年大阪万博の「太陽の塔」。やはり当初は閉幕後に解体する予定だったが、存続を願う運動が起こり、今も万博記念公園に残る。塔の内部も一般公開されている。藤本さんは「愛着だけではお金は生まれないから、簡単な話でもない」とし、「(僕らが)その時代の建築家から何かを受け取って何かを作ってきたように、自分も未来に貢献できればいいなという思いもある。今の心境としては、文化を作り上げ、持続させていきたい」と話す。
間違いなく人々の記憶に刻まれるであろう大屋根リング。できることなら、そのままの形で残し、2025年大阪・関西万博のシンボルとして人々に愛され続けてほしい。
文/仲底まゆみ
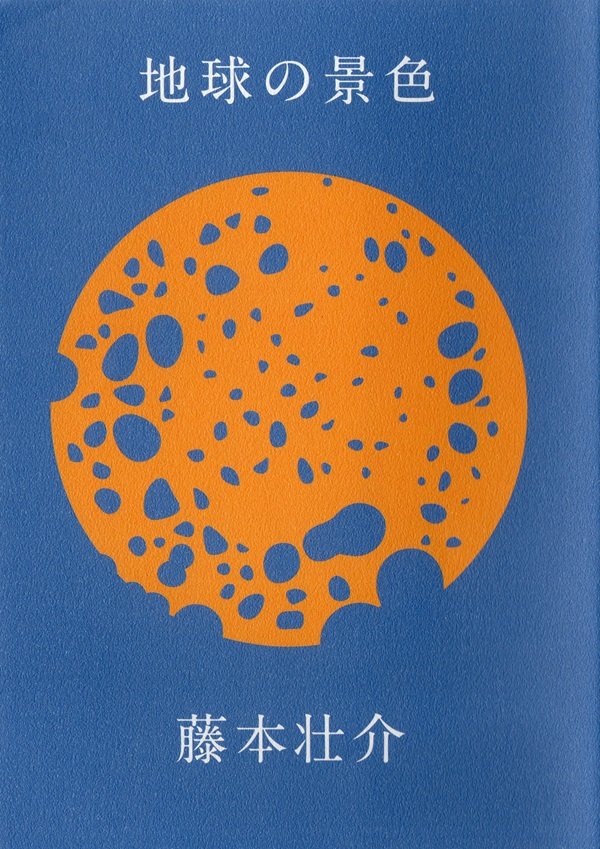
藤本さんの著書『地球の景色』(A.D.A.EDITA Tokyo)。藤本建築の思想をひも解くエッセーで、「屋根がなくても、屋根がないことによって、建築は建築を超えて『場』となり得る」とつづる

ふじもと・そうすけ
1971年北海道生まれ。東京大学工学部建築学科を卒業後、2000年に藤本壮介建築設計事務所を設立。14年にフランス・モンペリエ国際設計競技最優秀賞(ラルブル・ブラン)を受賞したほか、世界各国の国際設計競技で最優秀賞に輝く。11月9日まで、東京・六本木の森美術館で展覧会「藤本壮介の建築:原初・未来・森」 を開催中。
※記載内容は掲載時のデータです。
(出典:旅行読売2025年9月号)
(Web掲載:2025年8月1日)






 Tweet
Tweet Share
Share